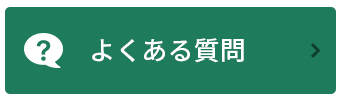肝疾患について
肝臓は右上腹部に位置する、腹部の臓器の中では最も大きなものです。「沈黙の臓器」とも呼ばれ、病気が進行しても自覚症状が出にくい特徴があります。そのため、病気の発見には無症状の状態での定期的な検査による早期発見が重要です。当院では、以下のような肝疾患の診療を行っています。
健診で指摘された肝機能障害の精密検査
健康診断で肝機能異常を指摘された場合、原因を特定し、適切な対策を講じることが重要です。通常以下のような精密検査を行います。
健診での肝機能障害は、脂肪肝、ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害などが原因であることが多いため、適切な診断と経過観察が重要です。当院では、精密検査を通じて早期発見・早期治療を行っております。
- 血液検査:AST、ALT、γ-GTP、ALP、ビリルビン、アルブミン、HBs抗原(B型肝炎)、HCV抗体(C型肝炎)、抗核抗体(自己免疫性肝炎)・抗ミトコンドリア抗体(原発性胆汁性胆管炎)などを測定し、肝障害の原因を調べます。
- 腹部超音波検査(エコー):肝臓の形態や脂肪の蓄積、腫瘍の有無を確認します。
- 肝硬度測定:エコーを用い肝臓の硬さを測定し、肝線維化の程度を評価、肝硬変のリスクを判定します。
- MRI・CT検査:エコーで異常がある時など、詳細な画像診断が必要な場合に実施します。必要時総合病院に依頼します。
- 肝生検(必要時):診断が難しい場合、肝組織を採取して詳しく調べることがあります。入院が必要なため総合病院に依頼します。
健診での肝機能障害は、脂肪肝、ウイルス性肝炎、アルコール性肝障害などが原因であることが多いため、適切な診断と経過観察が重要です。当院では、精密検査を通じて早期発見・早期治療を行っております。
1. 脂肪肝・MASLD・MASH
脂肪肝とは、肝臓に脂肪が蓄積する状態を指します。健診受診者の35%程度に認められ、程度の差こそあれ約1/3の人が脂肪肝と診断されます。近年、従来の「非アルコール性脂肪肝疾患(NAFLD)」の名称が見直され、新たに「代謝異常に関連した脂肪肝疾患(MASLD)」という名称が提唱されました。MASLDは、肥満や糖尿病・高血圧・低HDL血症・高中性脂肪血症などメタボリックシンドロームと密接な関係があります。
MASLDが進行すると、炎症や線維化を伴う「代謝異常に関連した脂肪肝炎(MASH)」に移行し、肝硬変や肝がんへ進行するリスクが高まります。
主な原因:肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常・メタボリックシンドローム・不規則な食生活。その他、薬剤・遺伝性代謝疾患・妊娠等も原因となることがあります。
症状:初期はほとんど無症状
治療:食事療法、運動療法、生活習慣の改善・減量
MASLDが進行すると、炎症や線維化を伴う「代謝異常に関連した脂肪肝炎(MASH)」に移行し、肝硬変や肝がんへ進行するリスクが高まります。
主な原因:肥満・糖尿病・高血圧・脂質異常・メタボリックシンドローム・不規則な食生活。その他、薬剤・遺伝性代謝疾患・妊娠等も原因となることがあります。
症状:初期はほとんど無症状
治療:食事療法、運動療法、生活習慣の改善・減量
脂肪肝の適切な経過観察の方法
脂肪肝は進行するとMASHや肝硬変に移行する可能性があるため、適切な経過観察が重要です。特に採血検査の数値異常がある方は要注意です。
体重が5%減少すると肝臓の脂肪含有量が減少し、7%減少すると炎症と非アルコール性脂肪肝炎が軽減し、10%減少すると瘢痕化と線維化の回復に役立つと言われています。体重超過のある方にはまずは“5%の減量”という提案をさせていただくことが多いです。
当院では、患者さまの病状に合わせた適切な経過観察と治療方針をご提案いたします。
- 定期的な血液検査:肝機能(AST、ALT、γ-GTP)、脂質異常、血糖値などをチェックし、異常がないか確認します。
- 超音波検査(エコー):脂肪肝の進行度を評価し、MASHや肝硬変への進行の兆候をチェックします。
- 肝硬度測定:肝線維化の有無を確認し、病気の進行リスクを評価します。
- 生活習慣の見直し:体重管理や食生活の改善、適度な運動の継続を推奨します。
- 合併症の管理:脂肪肝は糖尿病や高血圧・脂質異常とも関連が深いため、関連疾患のコントロールも重要です。
体重が5%減少すると肝臓の脂肪含有量が減少し、7%減少すると炎症と非アルコール性脂肪肝炎が軽減し、10%減少すると瘢痕化と線維化の回復に役立つと言われています。体重超過のある方にはまずは“5%の減量”という提案をさせていただくことが多いです。
当院では、患者さまの病状に合わせた適切な経過観察と治療方針をご提案いたします。
2. 肝炎(急性肝炎・慢性肝炎)
肝炎は、ウイルスやアルコール、自己免疫などが原因で肝臓に炎症が起こる疾患です。急性と慢性の肝炎があります。ここでは慢性の肝疾患について記載します。
主な症状:倦怠感、食欲不振、黄疸、尿の色の変化
治療:ウイルス性肝炎は抗ウイルス療法や肝庇護療法、アルコール性肝炎は禁酒、自己免疫性肝炎は肝庇護や免疫抑制剤(ステロイドなど)の使用
- ウイルス性肝炎(B型・C型肝炎):B型・C型肝炎ウイルスによって感染し、慢性化すると肝硬変や肝がんのリスクが高まります。
- アルコール性肝炎:過度な飲酒によって肝臓に炎症が生じる疾患。
- 自己免疫性肝炎:自己免疫の異常により自己の免疫細胞に肝細胞が攻撃される病気。
主な症状:倦怠感、食欲不振、黄疸、尿の色の変化
治療:ウイルス性肝炎は抗ウイルス療法や肝庇護療法、アルコール性肝炎は禁酒、自己免疫性肝炎は肝庇護や免疫抑制剤(ステロイドなど)の使用
B型慢性肝炎の抗ウイルス療法
B型慢性肝炎では、ウイルスの増殖を抑えるために抗ウイルス薬を使用することがあります。現在使用されている主な薬剤には以下のものがあります。
核酸アナログ製剤(エンテカビル、テノホビル、ラミブジンなど):ウイルスの増殖を抑制し、肝炎の進行を防ぐ目的で使用。
インターフェロン療法:免疫を活性化させてウイルスを排除する治療法(現在では使用頻度が低下)。
抗ウイルス療法は長期間にわたることが多く、適切な治療管理が必要です。当院では、核酸アナログ製剤の処方や定期的な採血や超音波(エコー)検査目的の通院が可能です。患者さまの病状に応じた最適な治療を提案いたします。
核酸アナログ製剤(エンテカビル、テノホビル、ラミブジンなど):ウイルスの増殖を抑制し、肝炎の進行を防ぐ目的で使用。
インターフェロン療法:免疫を活性化させてウイルスを排除する治療法(現在では使用頻度が低下)。
抗ウイルス療法は長期間にわたることが多く、適切な治療管理が必要です。当院では、核酸アナログ製剤の処方や定期的な採血や超音波(エコー)検査目的の通院が可能です。患者さまの病状に応じた最適な治療を提案いたします。
C型慢性肝炎の抗ウイルス治療後の経過観察
C型慢性肝炎の抗ウイルス治療(DAA療法など)は、通常精密検査を施行の上総合病院で行っています。しかし、ウイルスが排除された後も、定期的な経過観察が重要です。毎回総合病院への通院は大変なため、ウイルス除去後の経過観察は当院にて可能です。現在も多数の方を経過観察しています。
治療後も定期的な診察を受けることで、肝疾患の再発や進行を防ぐことができます。当院では、患者さま一人ひとりに合わせたフォローアップを行っております。
- 肝硬変や肝がんのリスク:特に、治療前に肝硬変がある場合は、ウイルスが排除された後も肝がんのリスクが強く残るため、3~6ヶ月ごとの超音波検査や腫瘍マーカー(AFP、PIVKA-Ⅱ)測定を推奨します。肝硬変がない方も6ヶ月毎程度の採血と超音波検査が推奨です。
- 肝機能のチェック:定期的な血液検査を行い、肝機能の維持を確認します。
- 生活習慣の管理:肥満や糖尿病がある場合は脂肪肝の合併も多い為、進行を防ぐために適切な食事・運動習慣を継続することが大切です。禁酒は継続しましょう。
- 食道静脈瘤の確認:慢性の肝疾患があると肝臓に血流が流れにくくなり食道や胃の周囲の血管に血流が増加し耐えられなくなった血管がコブのように膨らみ静脈瘤となることがあります。定期的な胃カメラ検査が推奨されます。
治療後も定期的な診察を受けることで、肝疾患の再発や進行を防ぐことができます。当院では、患者さま一人ひとりに合わせたフォローアップを行っております。
3. 肝硬変
肝硬変は、慢性的な炎症により肝臓が線維化し、硬く変わり、正常な機能を失っていく病気です。進行すると肝がんのリスクが高まり、様々な合併症が発生します。
主な原因:B型・C型肝炎、アルコール性肝炎、MASLD/MASH、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、など主な症状:腹水、黄疸、出血傾向、意識障害治療:肝硬変を元に戻すことは困難です。病気の進行を抑えるための食事療法、薬物療法、場合によっては肝移植
主な原因:B型・C型肝炎、アルコール性肝炎、MASLD/MASH、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、など主な症状:腹水、黄疸、出血傾向、意識障害治療:肝硬変を元に戻すことは困難です。病気の進行を抑えるための食事療法、薬物療法、場合によっては肝移植
4. 肝がん
肝がん(肝細胞癌)は、慢性的な肝疾患が進行した結果として発生することが多い病気です。慢性的な肝疾患のない方に肝がんが発生することは稀です。
主な原因:B型・C型肝炎・アルコール・脂肪肝などによる肝硬変
主な症状:初期は無症状、進行すると体重減少、腹部膨満感、倦怠感、黄疸など
治療:外科手術、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)、分子標的薬など
主な原因:B型・C型肝炎・アルコール・脂肪肝などによる肝硬変
主な症状:初期は無症状、進行すると体重減少、腹部膨満感、倦怠感、黄疸など
治療:外科手術、ラジオ波焼灼療法(RFA)、肝動脈化学塞栓療法(TACE)、分子標的薬など
肝疾患の早期発見・予防
肝臓病は早期発見が鍵となります。定期的な健康診断や血液検査、超音波検査を受けることで、肝疾患を早期に発見し、適切な治療を行うことが可能です。
当院では、肝臓の診療を行っておりますので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。いずれの原因でも禁酒は最低限必要です。
当院では、肝臓の診療を行っておりますので、気になる症状がある方はお気軽にご相談ください。いずれの原因でも禁酒は最低限必要です。