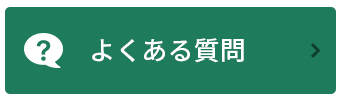がん検診について
がん検診は、がんの早期発見・早期治療に重要な役割を果たします。適切な受診間隔と検査内容を理解し、定期的に受診することが大切です。
がん検診には対策型健診と任意型健診があり検査方法や費用が異なります。
がん検診には対策型健診と任意型健診があり検査方法や費用が異なります。
対策型健診
集団からがんの疑いのある人を見つけ出し、早期発見・早期治療に結び付けて全体の脂肪率を減少させることを目的として実施するもの。市町村の行う住民検診や職場で行う職域検診がこれに該当します。公共的な予防対策のため、費用は公的補助金により、無料または少額の自己負担となります。科学的根拠に基づく有効性の確立した方法で実施されます。
任意型健診
個人が自分の死亡リスクを下げるために受けるもので、人間ドックがその代表です。費用は原則自己負担ですが、健康保険組合によって補助が出る場合があります。検査内容は個人の裁量によって選ぶことになりますのでそれぞれの検査法のメリットとデメリットを吟味することが大切です。
がんの種類別 対策型検診と任意型検診の違い
対策型検診で受けられるがん検診は、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの5つです。この5つのがんについて、それぞれ対策型検診と任意型検診の違いを紹介します。
がん検診の適切な間隔と検査方法
1.胃がん検診
| 検診方法 | 対策型検診 | 任意型検診 |
| 検診対象者 | 50歳以上の男女 | 希望者(特に定められていない) |
| 受診間隔 | 2年に1回 | 任意 |
| 検査方法 | 問診 胃部X線検査(バリウム検査)または 胃内視鏡検査(胃カメラ)のいずれか |
胃部X線検査(バリウム検査) 胃内視鏡検査(胃カメラ)など |
※市区町村によっては、胃X線検査を40歳以上から実施している場合もあります。
2.大腸がん検診
| 検診方法 | 対策型検診 | 任意型検診 |
| 検診対象者 | 40歳以上の男女 | 希望者(特に定められていない) |
| 受診間隔 | 1年に1回 | 任意 |
| 検査方法 | 問診および便潜血検査 | 便潜血検査 大腸X線検査 大腸内視鏡検査(大腸カメラ)など |
※便潜血検査で異常が見つかった場合は、必ず精密検査として大腸内視鏡検査を行います。
3.肺がん検診
| 検診方法 | 対策型検診 | 任意型検診 |
| 検診対象者 | 40歳以上の男女 | 希望者(特に定められていない) |
| 受診間隔 | 1年に1回 | 任意 |
| 検査方法 | 問診 胸部X線検査 および喀痰細胞診検査 |
胸部X線検査 胸部CT 呼吸機能検査など |
喀痰細胞診
肺がんの場合、がん細胞が痰の中に剥がれ落ちることがあるため、痰を調べてがん細胞を検出します。3日間、できる限り起床時の早朝に採取した痰を検査します。
※ 喀痰細胞診検査は、喫煙指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が600以上となる50歳以上の方を対象に行います。
肺がんの場合、がん細胞が痰の中に剥がれ落ちることがあるため、痰を調べてがん細胞を検出します。3日間、できる限り起床時の早朝に採取した痰を検査します。
※ 喀痰細胞診検査は、喫煙指数(1日喫煙本数×喫煙年数)が600以上となる50歳以上の方を対象に行います。
4.乳がん検診
| 検診方法 | 対策型検診 | 任意型検診 |
| 検診対象者 | 40歳以上の女性 | 希望者(特に定められていない) |
| 受診間隔 | 2年に1回 | 任意 |
| 検査方法 | 問診 乳房X線検査(マンモグラフィ) |
触診および 乳房X線検査(マンモグラフィ) 乳腺超音波など |
乳がんの発見の約半数は自己発見です。日ごろから自分の乳房の状態を知り異常があれば乳腺外科を受診しましょう。
※視診・触診は推奨されていません。 実施する場合はマンモグラフィと併用。
※視診・触診は推奨されていません。 実施する場合はマンモグラフィと併用。
5.子宮頸がん検診
| 検診方法 | 対策型検診 | 任意型検診 |
| 検診対象者 | 20歳以上の女性 | 希望者(特に定められていない) |
| 受診間隔 | 2年に1回 | 任意 |
| 検査方法 | 問診、視診 子宮頸部の細胞診および 内診(必要に応じてコルポスコープ検査を行う) |
子宮頸部の細胞診および内診 HPV検査(単独法) HPV検査と細胞診の同時併用法 HPV検査陽性者への細胞診トリアージ法など |
※市区町村が導入した場合、30歳以上を対象にHPV検査単独法が5年に1回の頻度で実施されることがあります。
対策型健診としては勧められておらず、任意型健診として施行可能なもの
6. 前立腺がん(男性のみ)
死亡率減少効果の有無を判断する証拠が現状では不十分であるため、現在のところ対策型検診としては勧められていません。任意型検診として行う場合には、受診者に対して、効果が不明であることと、過剰診断などの不利益について適切に説明する必要があります。
当院では“がん”で苦しむ患者様を少しでも減らせるように、早期発見・早期治療に力を入れています。ご自身の健康管理のため、ぜひ適切な間隔での受診をご検討ください。
- 対象年齢:50歳以上(推奨される年齢は地域による)
- 受診間隔:1年に1回(推奨される場合)
- 検査方法:PSA(前立腺特異抗原)検査
死亡率減少効果の有無を判断する証拠が現状では不十分であるため、現在のところ対策型検診としては勧められていません。任意型検診として行う場合には、受診者に対して、効果が不明であることと、過剰診断などの不利益について適切に説明する必要があります。
当院では“がん”で苦しむ患者様を少しでも減らせるように、早期発見・早期治療に力を入れています。ご自身の健康管理のため、ぜひ適切な間隔での受診をご検討ください。