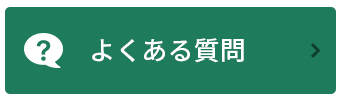おなかの症状について
おなかの症状について
おなかの症状の原因・臓器は様々です。症状の場所・性状(痛み、張り、胸やけ、出血など)・持続する時間・随伴症状(発熱・嘔吐・便通異常など)などから原因を推測しますが、診断の確定は簡単ではありません。
原因としては、胃・腸などの消化管、肝臓・胆のう・膵臓などの消化器系臓器の病気だけでなく、腎臓・膀胱などの尿路系、子宮・卵巣などの婦人科系の病気のこともあります。
通常、問診・診察をしながら5~10個の鑑別診断を頭の中で挙げながら可能性の高い疾患・緊急で除外したい疾患を考えています。
原因としては、胃・腸などの消化管、肝臓・胆のう・膵臓などの消化器系臓器の病気だけでなく、腎臓・膀胱などの尿路系、子宮・卵巣などの婦人科系の病気のこともあります。
通常、問診・診察をしながら5~10個の鑑別診断を頭の中で挙げながら可能性の高い疾患・緊急で除外したい疾患を考えています。
受診の目安
以下のような症状を伴う場合は、早めの受診をおすすめします。
- 強い痛み、突然の痛み
- 発熱、嘔吐を伴う
- 血尿や血便など出血が見られる
- 痛みが長時間続く、または悪化する
- 飲食ができない、動けないなど全身状態不良な状態
検査
腹部だけに限りませんが、正確な診断をするためには丁寧な問診・診察を行い症状の原因と思われる疾患・部位の推測をしていきます。必要に応じ各種検査を追加していきます。
通常、侵襲やコストが低く、広く浅くを目的とした原因の場所を絞ることができる検査から行います。必要であれば的を絞った検査(場合によって侵襲がありコストが高い検査)に移行していきます。食道や胃・十二指腸の病気が疑われる場合には胃カメラ検査、大腸の病気が疑われる場合には大腸カメラ検査、エコーで分かりにくい部位の精密検査としてCT検査などを行います。
当院の強みとしては、腹部・心臓を含め多くの部位の超音波(エコー)検査が高精度でできること、胃・大腸カメラができること、それによって多くの疾患の検索ができることです(申し訳ありませんが婦人科・乳腺エコーには対応していません)。気になる症状がある場合はご相談ください。
通常、侵襲やコストが低く、広く浅くを目的とした原因の場所を絞ることができる検査から行います。必要であれば的を絞った検査(場合によって侵襲がありコストが高い検査)に移行していきます。食道や胃・十二指腸の病気が疑われる場合には胃カメラ検査、大腸の病気が疑われる場合には大腸カメラ検査、エコーで分かりにくい部位の精密検査としてCT検査などを行います。
当院の強みとしては、腹部・心臓を含め多くの部位の超音波(エコー)検査が高精度でできること、胃・大腸カメラができること、それによって多くの疾患の検索ができることです(申し訳ありませんが婦人科・乳腺エコーには対応していません)。気になる症状がある場合はご相談ください。
心窩部痛(みぞおちの痛み)について
心窩部(みぞおちのあたり)の痛みを感じる症状です。胃が痛い・みぞおちが痛い・臍の上の方が痛いなどと表現されます。
胃が痛い、と訴えて受診される方の中には、胃の病気だけではなく、十二指腸や胆のう・膵臓・腸など他の消化器系の病気以外にも心臓の病気が隠れていることもあります。比較的便秘の症状の方も多く見受けられます。
胃が痛い、と訴えて受診される方の中には、胃の病気だけではなく、十二指腸や胆のう・膵臓・腸など他の消化器系の病気以外にも心臓の病気が隠れていることもあります。比較的便秘の症状の方も多く見受けられます。
検査
胃が原因である可能性が高い場合には胃カメラ検査を行います。胃以外の消化器の病気を考える場合には、血液検査や腹部レントゲン撮影、腹部超音波(エコー)検査を行います。胃の中は胃カメラで、胃の外は腹部超音波(エコー)検査で調べるのが一般的です。
心臓が原因の可能性がある場合には心電図や血液検査、心臓超音波(エコー)検査などを実施します。胃が痛いと言っているから胃カメラ、というのは正しくありません。
心臓が原因の可能性がある場合には心電図や血液検査、心臓超音波(エコー)検査などを実施します。胃が痛いと言っているから胃カメラ、というのは正しくありません。
心窩部痛の主な原因
- 胃の問題:胃(十二指腸)潰瘍・胃炎・アニサキス症・胃がん・機能性胃腸症(機能性ディスペプシア)
- 胆嚢の問題:胆石症・胆嚢炎(胆管炎)・胆のうがん
- 膵臓の問題:急性膵炎・慢性膵炎・膵石症・膵がん
- 腸の問題:大腸炎・小腸炎・腸閉塞・大腸がん・過敏性腸症候群
- 心臓の問題:心筋梗塞・狭心症・不整脈・大動脈解離・動脈瘤破裂
下腹部痛について
下腹部痛は、多くの方が経験するよくある症状です。しかし、その原因はさまざまです。痛みの場所・程度・持続時間、その他の症状によって、軽度なものから早急な対応が必要な疾患まで幅広く考えられます。また、消化器疾患から婦人科・泌尿器・整形外科まで由来臓器も様々です。
検査
問診・診察である程度の原因臓器の推測をします。必要に応じ腹部レントゲン、腹部超音波(エコー)、CTや内視鏡検査を検討します。
下腹部痛の主な原因
胃もたれについて
胃もたれとは、食べ物の消化が遅い事によって生じる上腹部の不快感です。胃が重たい、苦しい、張っているなど訴えはさまざまです。飲酒・暴飲暴食・脂っこいものを取り過ぎた後に感じることが多いですが、感染症や体調不良時の初期症状として感じることもあります。一時的(数日程度)な症状であれば心配ないことも多いですが、症状が持続・悪化する場合は検査をお勧めします。
検査
胃などの消化管が原因である可能性が高い場合には胃カメラ検査を行います。胃以外の消化器系の病気の可能性がある場合には、血液検査や腹部レントゲン撮影、腹部超音波(エコー)検査などを行います。胃の中は胃カメラで、胃の外は腹部超音波(エコー)検査で調べるのが一般的です。
胃もたれの主な原因
- 慢性胃炎・胃潰瘍・逆流性食道炎・ピロリ菌感染
- 機能性胃腸症
- 加齢・ストレス
- 飲酒・暴飲暴食・早食いなど
吐き気・嘔吐について
吐き気は前胸部や心窩部(みぞおちのあたり)がムカムカとする不快感です、悪化すると嘔吐してしまうこともあります。嘔吐下痢症などの消化管の病気が原因の事が多いですが、その他消化器系疾患(腸閉塞や腹部の炎症性疾患など)・心臓疾患(不整脈・心筋虚血など)、頭蓋内疾患(脳出血・くも膜下出血・脳梗塞・脳腫瘍など)、めまい、つわり、薬の副作用など原因は非常に多岐にわたります。急を要する病気が起こっている可能性もありますので、強い症状・持続する症状がある場合は医療機関を受診ください。
検査
詳しい問診を行い原因部位の推測をします。持病の確認や飲んでいる薬の確認、その他の症状の確認なども同時に行います。その上で必要と考えられる検査を行います。
腹部・胸部・頭部・など必要に応じ疑われる部位の検査を行います。
腹部・胸部・頭部・など必要に応じ疑われる部位の検査を行います。
吐き気・嘔吐の主な原因
- 消化器系の問題:胃腸炎(嘔吐下痢症)・胃十二指腸潰瘍・胃癌
- 中枢神経系の問題:頭痛(片頭痛など)・脳腫瘍や脳出血やくも膜下出血
- 内耳の問題:めまい(メニエール病など)
- 循環器系の問題:心筋梗塞・不整脈
- その他:薬剤性・妊娠(つわり)・高血糖や低血糖
胸焼けについて
胸焼けは胸から心窩部(みぞおちのあたり)にかけてヒリヒリと焼ける様な感じやしみるような感じ、口の中がすっぱいような苦いような感じ、げっぷが多い、などが訴えられます。胃酸が胃から食道へ逆流することで胸焼けが起こることが多いです。
最も多いものは逆流性食道炎ですが、食道がんや胃がんでも通過障害が生じると同様の症状を訴えられることがあるため注意を要します。
最も多いものは逆流性食道炎ですが、食道がんや胃がんでも通過障害が生じると同様の症状を訴えられることがあるため注意を要します。
検査
生活習慣の指導、胃酸を抑える薬の処方をしたり、胃カメラ検査を提案します。
胸やけの主な原因
- 逆流性食道炎・機能性胃腸症
- 食生活(飲酒・カフェイン・香辛料の摂取など)
- 生活習慣(喫煙・ストレス・肥満・睡眠不足など)
- 妊娠(つわり)
喉(のど)がつかえる、食べ物がつかえる
喉がつかえる症状は、喉や食道の病気が原因で起こることがありますが、脳梗塞後などで飲み込む能力の低下(誤嚥)で起こることもあります。
喉がつかえる、喉に違和感がある、食べ物が飲み込みづらい、食べ物がつまってうまく流れていかない、などの症状があれば医療機関を受診することをお勧めします。逆流性食道炎・食道がん・咽喉頭がん・嚥下機能の低下などが無いかを検索します。
喉がつかえる、喉に違和感がある、食べ物が飲み込みづらい、食べ物がつまってうまく流れていかない、などの症状があれば医療機関を受診することをお勧めします。逆流性食道炎・食道がん・咽喉頭がん・嚥下機能の低下などが無いかを検索します。
検査
胃カメラ検査を検討します、耳鼻科の先生へご紹介させていただくことも可能です。麻痺や嚥下機能の評価が必要な場合があります。
喉(のど)がつかえる、食べ物がつかえる主な原因
- 逆流性食道炎・食道がん・咽喉頭がん
- 咽喉頭異常感症(ヒステリー球) ストレスなどで喉に異物感を感じる状態
- 感染症、アレルギー性鼻炎
- 精神的問題
- 甲状腺疾患
消化管出血(下血・血便・吐血など)
口から肛門までは1本道のためどこかから出血すると口または肛門から血液混じりの吐物または排せつ物が出てきます。
主に口に近い消化管(食道・胃・十二指腸・上部小腸など)からの出血は下血(黒い便・タール状の便)、肛門に近い消化管(下部小腸・大腸・肛門など)からの出血は血便(赤い便・赤黒い便)と呼ばれます。血液混じりの嘔吐をすることを吐血と言い、基本的に食道・胃・十二指腸からの出血と考えます。咳き込んだ際に血が混じる・痰に血が付く場合は気道(肺や気管支)からの出血と考え、喀血・血痰と呼び区別されます。きちんと問診できればほとんど区別できます。
口ではうまく伝えられないという方は写真を撮っていただき、診察時に見せていただくのが伝わりやすいです。放置しても良い消化管出血は原則ありませんので早期の受診を推奨します。
主に口に近い消化管(食道・胃・十二指腸・上部小腸など)からの出血は下血(黒い便・タール状の便)、肛門に近い消化管(下部小腸・大腸・肛門など)からの出血は血便(赤い便・赤黒い便)と呼ばれます。血液混じりの嘔吐をすることを吐血と言い、基本的に食道・胃・十二指腸からの出血と考えます。咳き込んだ際に血が混じる・痰に血が付く場合は気道(肺や気管支)からの出血と考え、喀血・血痰と呼び区別されます。きちんと問診できればほとんど区別できます。
口ではうまく伝えられないという方は写真を撮っていただき、診察時に見せていただくのが伝わりやすいです。放置しても良い消化管出血は原則ありませんので早期の受診を推奨します。
血便・下血の原因
下血(黒色便・タール便)が出た場合
上部消化管(食道・胃・十二指腸)から出た血液が、胃酸により酸化することから黒色になります。黒色便やタール便ということもあります。
下血(黒色便・タール便)を認めた際には、緊急性の高い病気が原因のことがあるため、早期の胃カメラ検査を検討します。必要に応じ総合病院などに当日紹介します。
食道の病気
胃の病気
十二指腸の病気
血便(赤い便・赤黒い便)が出た場合
肛門に近いほど真っ赤な鮮血になり、肛門から遠いほど赤黒くなります。
腸の炎症を伴っている場合、血液に加えて腸からのベタベタした粘液が混ざっている場合があり粘血便と言います。潰瘍性大腸炎・クローン病・感染による大腸炎などで認められます。これらの症状を認めた際には大腸カメラやCT検査などを行います。
大腸の病気
上部消化管(食道・胃・十二指腸)から出た血液が、胃酸により酸化することから黒色になります。黒色便やタール便ということもあります。
下血(黒色便・タール便)を認めた際には、緊急性の高い病気が原因のことがあるため、早期の胃カメラ検査を検討します。必要に応じ総合病院などに当日紹介します。
食道の病気
- 食道静脈瘤破裂
- 食道がん
- マロリー・ワイス症候群(Mallory-Weiss症候群)
胃の病気
- 胃潰瘍
- 胃がん
- 急性胃粘膜病変(AGML:Acute Gastric Mucosal Lesion)
- 胃静脈瘤破裂
十二指腸の病気
- 十二指腸潰瘍
血便(赤い便・赤黒い便)が出た場合
肛門に近いほど真っ赤な鮮血になり、肛門から遠いほど赤黒くなります。
腸の炎症を伴っている場合、血液に加えて腸からのベタベタした粘液が混ざっている場合があり粘血便と言います。潰瘍性大腸炎・クローン病・感染による大腸炎などで認められます。これらの症状を認めた際には大腸カメラやCT検査などを行います。
大腸の病気
- 大腸がん
- 大腸ポリープ
- 憩室出血(大腸に認められる小部屋からの出血)
- 感染性腸炎
- 炎症性腸疾患(潰瘍性大腸炎・クローン病・ベーチェット病など)
- 直腸潰瘍
- 放射線性腸炎(前立腺がんなどで放射線治療後の方)
- 痔
血便・下血の際の検査
- 血液検査
- CT検査
- 胃カメラ検査・大腸カメラ検査(内視鏡検査)
検診で、便潜血陽性と言われたら
便潜血検査(大腸がん検診)は便の中に血液が混じっていないかを調べる検査です。大腸がんの早期発見に有効とされていることから、現在日本では40歳以上で年1回の定期的な検査が勧められています。
便潜血検査の陽性率は5~7%程度、陽性反応が出た方に大腸がんが発見される確率は2~3%程度と言われています。その他、ポリープ・痔・炎症・便秘などで陽性になることがあります。他の病気が見つかることもあるため、便潜血検査で一度でも陽性を指摘された場合には医療機関へ受診、大腸カメラを推奨します。もう1回便潜血検査、は間違いです。
便秘について
便秘は新たに、「本来排泄すべき糞便が大腸内に滞ることによる兎糞状便・硬便,排便回数の減少や,糞 便を快適に排泄できないことによる過度な怒責, 残便感,直腸肛門の閉塞感,排便困難感を認める状態」と定義されました。簡単に言うと、硬くて出にくい・週3回未満の排便・強くいきむ必要がある・残便感を感じる・閉塞感や排便困難感がある・摘便や圧迫による介助を要する状態、と考えられます。
便秘は生活の質(QOL)を下げることが多く、生活習慣の改善だけでは便秘の解消が難しい場合にはお薬の治療を行っていきます。また、急に便秘傾向となったり、腹痛や便に血が混ざるなどの症状があったりする場合には、大腸がんなどの深刻な病気の可能性もあるため、放置せず医療機関を受診・大腸カメラを検討されることをお勧めします。
便秘は生活の質(QOL)を下げることが多く、生活習慣の改善だけでは便秘の解消が難しい場合にはお薬の治療を行っていきます。また、急に便秘傾向となったり、腹痛や便に血が混ざるなどの症状があったりする場合には、大腸がんなどの深刻な病気の可能性もあるため、放置せず医療機関を受診・大腸カメラを検討されることをお勧めします。
便秘と腹痛
便秘でお腹が痛くなる・お腹が張ることはよくあります。便秘というと「腸の問題」と考え、下腹部痛になると思われがちですが、小腸から大腸までお腹全体に腸は配置されているため、便秘によるお腹の痛みの中には上腹部痛となることも頻繁にあります。
特に、みぞおちが痛く、食べるとお腹が張って吐き気を感じたりすると、「胃が原因かな?」と思うかもしれません。しかし、痛みの部位で臓器を特定するのは容易ではありません。医師でも確定は難しいので患者さんにはほとんど不可能と思います。胃が痛いからよそで胃カメラをしてもらったけど何もなかった、良くならない、と来院される方は多数います。胃が痛いから胃カメラを、と安易に判断するのは間違いです。お腹の痛みが続くときは、一度当院へご相談ください。
特に、みぞおちが痛く、食べるとお腹が張って吐き気を感じたりすると、「胃が原因かな?」と思うかもしれません。しかし、痛みの部位で臓器を特定するのは容易ではありません。医師でも確定は難しいので患者さんにはほとんど不可能と思います。胃が痛いからよそで胃カメラをしてもらったけど何もなかった、良くならない、と来院される方は多数います。胃が痛いから胃カメラを、と安易に判断するのは間違いです。お腹の痛みが続くときは、一度当院へご相談ください。
検査
まずは問診や腹部診察を行います。その上で必要に応じて、腹部レントゲン撮影や腹部超音波(エコー)などを検討します。腹痛の原因が大腸カメラで見つかることは通常ほとんどありませんので腹痛でいきなり大腸カメラは間違いです(緊急の大腸カメラはほぼ止血目的)。通過障害の有無を検索してから、排便コントロールをして、必要であれば大腸がんの検索をします(便を出さないと大腸カメラはできません)。
下痢について
下痢とは、「便形状が軟便あるいは水様便、かつ排便回数が増加する状態」、と定義されます。通常、正常な排便回数は個人差がありますが、2~3回/日~3回/週程度とされているため、下痢は水様の便が3回/日以上排出される状態と考えられます。
いわゆる、小腸炎(嘔吐下痢症など)の時の下痢は水様で尿のようにシャーっと出る下痢で嘔吐を伴うこともあります。大腸炎の下痢は発熱・腹痛・出血を伴うことがあり・粘液混じりで少量頻回の下痢が多くしぶり腹(頻繁に便意を伴うがあまり出ない状態)を伴うことがあると考えられ細菌性の可能性があります。
いわゆる、小腸炎(嘔吐下痢症など)の時の下痢は水様で尿のようにシャーっと出る下痢で嘔吐を伴うこともあります。大腸炎の下痢は発熱・腹痛・出血を伴うことがあり・粘液混じりで少量頻回の下痢が多くしぶり腹(頻繁に便意を伴うがあまり出ない状態)を伴うことがあると考えられ細菌性の可能性があります。
検査
まずは問診や腹部診察を行います。その上で必要に応じて、血液検査や腹部レントゲン撮影、腹部超音波(エコー)検査などを行います、大腸の炎症が疑われる場合は便の培養検査を提出することもあります。慢性的に下痢症状が続く場合には、大腸カメラ検査を実施し、腫瘍や炎症性腸疾患と言われる病気がないかなどを確認していきます。