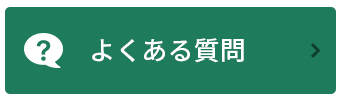食欲不振
食欲が低下する原因
数日で改善する急性のものから、徐々に悪化傾向を示す慢性のものまで原因は様々です。大きな症状もなくすぐに改善してしまう場合は経過観察で構いませんが、強い症状を伴ったり徐々に悪化・体重減少を伴う場合は原因検索が必要です。食欲が低下する原因をいくつか記載します。
1. 消化器系の病気
胃腸の不調があると、食欲が低下することがあります。
- 胃炎・胃潰瘍(胃の粘膜の炎症や傷)
- 逆流性食道炎(胃酸が逆流し、胸やけや食欲低下を引き起こす)
- 慢性便秘・腸の機能低下(腸にガスがたまり、食欲が低下)
- 肝臓・膵臓の病気(肝炎、肝硬変、膵炎など)
2. 感染症
体内にウイルスや細菌が侵入すると、免疫反応が起こり、食欲が低下することがあります。
- かぜ・インフルエンザなどの急性気道感染
- 胃腸炎・嘔吐下痢症(ノロウイルス・細菌性腸炎など)
- 肺炎や結核(発熱や倦怠感を伴うことが多い)
- 新型コロナウイルス感染症(味覚・嗅覚障害を伴うことも)
3. がん(悪性腫瘍)
進行したがんは、体のエネルギー消費が増え、食欲が低下することがあります。
- 胃がん・大腸がん・膵がん(消化器がんは特に食欲不振を引き起こしやすい)
- 消化器領域以外のがんでも進行すると食欲低下をひきおこします
- 全身の倦怠感・体重減少がある場合は、早めの検査が重要
4. 薬剤性
治療のために処方される薬剤によって食欲低下が起こることがあります。直接的な作用・効き過ぎによる作用・相乗効果作用などがあります。
痛み止めによる潰瘍、向精神薬(抗うつ薬・抗不安薬、睡眠薬など)や強い痛み止め(神経障害性疼痛・麻薬関連など)による便秘は高頻度で認められます。
痛み止めによる潰瘍、向精神薬(抗うつ薬・抗不安薬、睡眠薬など)や強い痛み止め(神経障害性疼痛・麻薬関連など)による便秘は高頻度で認められます。
- 消化管障害(胃炎・潰瘍など)
NSAIDs、ビスホスホネート製剤。定期で痛み止めを内服する場合は“evidence(根拠)のある胃薬“の併用が必要 - 嘔気、嘔吐
麻薬製剤、抗がん剤、SSRI(抗うつ剤)、ジギタリス製剤(強心剤)、鉄剤(造血剤)、ビタミンD製剤(骨粗鬆症薬)、テオフィリン製剤など - 便秘
抗コリン薬(鎮痙剤、排尿障害治療薬、抗パーキンソン、抗ヒスタミン薬、中枢性鎮咳薬、総合感冒薬など)
鎮痛剤、麻薬製剤、抗がん剤
向精神薬(中枢神経に作用し精神機能に影響を及ぼす薬剤(抗うつ薬・抗不安薬・睡眠薬等)) - 下痢
抗がん剤、抗菌薬、その他薬剤による副作用など - 味覚障害
苦みのある薬剤、キレート剤、抗がん剤、抗うつ薬、抗菌薬など
5. 内分泌・ホルモンの異常
ホルモンバランスの乱れによって、食欲が低下することがあります。
- 甲状腺機能低下症(基礎代謝が低下し、全身の倦怠感とともに食欲も減退)
- 糖尿病(血糖値の乱れにより、食欲が変化)
- 更年期障害(ホルモンバランスの変化により、食欲不振を引き起こすことも)
6. 精神的ストレス・自律神経の乱れ
ストレスや精神的な負担がかかると、自律神経が乱れ、食欲が低下することがあります。
- 過度なストレスや不安(仕事や人間関係など)
- うつ病・適応障害(気分の落ち込みとともに食欲が低下)
- 睡眠不足・疲労の蓄積(自律神経のバランスが崩れる)
7. 生活習慣の乱れ
不規則な生活や食事習慣の乱れが、食欲の低下につながることがあります。
- 偏った食生活(脂っこい食事・アルコールの過剰摂取)
- 運動不足(代謝が低下し、胃腸の働きが鈍くなる)
- 過度なダイエット(無理な食事制限・ホルモンバランスの不良)
まとめ
食欲不振が続く場合は、早めの受診を!
「食欲がないだけ」と思っていても、体の不調のサインかもしれません。2週間以上続く場合や、体重減少・持続する発熱・倦怠感を伴う場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
当クリニックでは、消化器の専門医による診察・検査(血液検査・腹部エコー・内視鏡検査など)を行い、適切な治療をサポートいたします。また、当然ですが原因が消化器疾患ではない方も多くらっしゃいます。当院では“医療の窓口”として、専門領域は専門性高く・その他の領域は総合的な診療・判断を行い診療していきます。それが適切な病診連携(専門診療を行う総合病院と総合診療を行うクリニックの連携)と考えています。お気軽にご相談ください。
「食欲がないだけ」と思っていても、体の不調のサインかもしれません。2週間以上続く場合や、体重減少・持続する発熱・倦怠感を伴う場合は、早めに医療機関を受診することをおすすめします。
当クリニックでは、消化器の専門医による診察・検査(血液検査・腹部エコー・内視鏡検査など)を行い、適切な治療をサポートいたします。また、当然ですが原因が消化器疾患ではない方も多くらっしゃいます。当院では“医療の窓口”として、専門領域は専門性高く・その他の領域は総合的な診療・判断を行い診療していきます。それが適切な病診連携(専門診療を行う総合病院と総合診療を行うクリニックの連携)と考えています。お気軽にご相談ください。