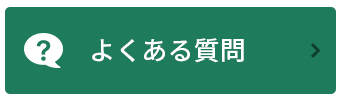大腸憩室炎
大腸憩室炎の原因と症状について
大腸憩室炎は、大腸の壁に認められる憩室と呼ばれる小さな袋状の突起ができ、その中に炎症が起こる病気です。憩室は先天性または後天性の原因で腸管内圧が上昇することで形成されます。後天性の主な原因に、便秘や食物繊維の摂取量の不足があげられています。原則、憩室が認められても炎症や出血がなければ治療対象にはなりません。
憩室自体は、高齢者に多く見られる一般的なものですが、炎症が起こることで痛みや発熱を引き起こします。大腸憩室炎は放置すると出血や穿孔・膿瘍形成など重篤な合併症を引き起こすことがあるため、早期に発見し適切な治療を行うことが重要です。以下に、大腸憩室炎の原因と症状について説明いたします。
憩室自体は、高齢者に多く見られる一般的なものですが、炎症が起こることで痛みや発熱を引き起こします。大腸憩室炎は放置すると出血や穿孔・膿瘍形成など重篤な合併症を引き起こすことがあるため、早期に発見し適切な治療を行うことが重要です。以下に、大腸憩室炎の原因と症状について説明いたします。
原因
- 食物繊維の摂取不足
食物繊維が不足すると、大腸内で便が硬くなり、腸管内の圧が高くなります。この圧力が長期間続くことで、大腸の壁が外側に突出し憩室と呼ばれる小部屋ができる原因となります。さらに、硬い便が憩室に詰まると、そこに細菌が繁殖し炎症を引き起こすことがあります。 - 加齢
加齢に伴い、大腸壁の筋肉が弱くなり、腸管壁に圧力がかかることにより憩室が形成されます。 - 便秘
便秘が慢性的に続くと、大腸内での圧が増加し、憩室の形成を促進します。便が憩室内に滞留することにより、炎症を引き起こすことがあります。 - 腸内フローラの乱れ
腸内の細菌バランスが崩れると、憩室内に細菌が異常繁殖し、炎症を引き起こすことがあります。 - 遺伝的要因
家族歴に大腸憩室炎のある人は、発症リスクが高いとされています。
症状
- 腹痛
最も一般的な症状で、激しい痛みを感じることがあります。痛みは持続的で、食後に強くなることがあります。右側の上行結腸、左下のS状結腸が比較的好発部位です。 - 発熱
炎症に伴い、軽度から中等度の発熱が見られることがあります。炎症が進行すると、高熱が出ることもあります。 - 下痢または便秘
大腸憩室炎では、便通異常を生じることがあります。炎症により急激に症状が悪化することがあるため、便通に異常を感じた場合は注意が必要です。下痢になることも、炎症で便秘になることもあります。 - 嘔気・嘔吐
腸の炎症や腹部の不快感により、嘔気や嘔吐が出現することがあります。 - 血便
炎症がひどくなると、大腸内で出血が起こり、血便が見られることがあります。血便は鮮やかな赤色のこともあれば、黒色便として現れることもあります。便の色でおおよその出血部位の推定ができます。 - 腹部膨満感
炎症で腸管の動きが悪くなることにより、腸管内でガスが溜まることでお腹が張り、膨満感を感じることがあります。特に食後にこの症状が強くなることがあります。
大腸憩室炎の診断と治療方法について
大腸憩室炎は、大腸の憩室に炎症が起こる疾患で、適切な診断と治療が重要です。治療が遅れると症状が悪化したり(穿孔(腸に穴が開いて膿が溜まる)、出血など)、合併症が発生する可能性があるため、早期の対応が求められます。以下に、大腸憩室炎の診断方法と治療方法について詳しくご説明いたします。
診断方法
- 問診・診察
症状(腹痛、発熱、下痢、便秘、血便など)を詳しく問診します。また、既往歴や生活習慣(食事内容や便通の状態など)についても確認します。
腹部を診察し、痛みの位置や程度を確認します。これにより、診断や腹膜炎の有無を評価します。 - 血液検査
炎症の程度を確認するために血液検査を行います。 - 画像検査
CT/エコー:大腸憩室炎の診断において有用な画像検査であり、炎症の広がりや合併症の有無を確認できます。CTは憩室の存在や、炎症の程度を詳細に把握できるため、診断の精度が高いです。エコーは被爆なく観察できるため女性や小児に行いやすく、必要に応じ使い分けをします。
大腸内視鏡検査(大腸カメラ):内視鏡を使用して大腸内を直接観察する検査です。憩室や炎症の状態、腫瘍の有無を確認することができますが、急性の炎症がある場合は通常内視鏡検査を避けることが推奨されます。通常炎症の改善後に腫瘍の有無検索を行います。
治療方法
- 保存的治療(軽症の場合)
薬物療法
・抗生物質:細菌をやっつけるために抗生物質を使用します。
・鎮痛薬:腹痛を和らげるために、鎮痛薬を使用することがあります。
・緩下剤:便通が改善することで腸内の圧力が軽減され、憩室の症状が和らぐ場合があります。
食事制限
初期の段階では、消化に負担の少ない食事(流動食や軽い食事)を摂ることが勧められます。急性期の症状が落ち着いたら、徐々に通常の食事に戻します。症状が強い場合や出血を伴う場合は入院の上絶食治療を要することがあります。 - 外科的治療(重症の場合)
手術療法:症状がひどく、保存的治療が効果を示さない場合や合併症(穿孔や膿瘍形成、腸閉塞など)が発生した場合には、外科的手術が必要になることがあります。手術では、炎症を起こした部分の大腸を切除することがあります。
緊急手術:穿孔や膿瘍形成、重度の腸閉塞などがある場合には、緊急手術が行われることがあります。 - 経過観察(軽症または回復後)
治療後は、再発を防ぐための経過観察が重要です。慢性の便通異常がある方は定期的に診察を受けていただき、排便コントロールを行います。
食事管理:食物繊維を十分に摂取することで便通を改善し、大腸内の圧を減らすことが予防に繋がります。生活習慣の見直しも推奨されます。
内視鏡検査:通常、炎症が改善した後で内視鏡検査を行います。大腸がんの有無の検索が推奨されます。
まとめ
大腸憩室炎は、早期に診断し適切な治療を行うことで、回復が早く、合併症を防ぐことができます。軽度の症状の場合は、保存的治療で改善することが多いですが、重症の場合は外科的治療が必要となることがあります。また、当初は軽症と診断され保存的治療を開始したものの徐々に悪化し重症化することもあるため経過観察を要します。
症状が現れた場合やご不安な点がある場合は、早期にご相談ください。当クリニックでは、迅速かつ適切な診断と治療を提供いたします。
症状が現れた場合やご不安な点がある場合は、早期にご相談ください。当クリニックでは、迅速かつ適切な診断と治療を提供いたします。